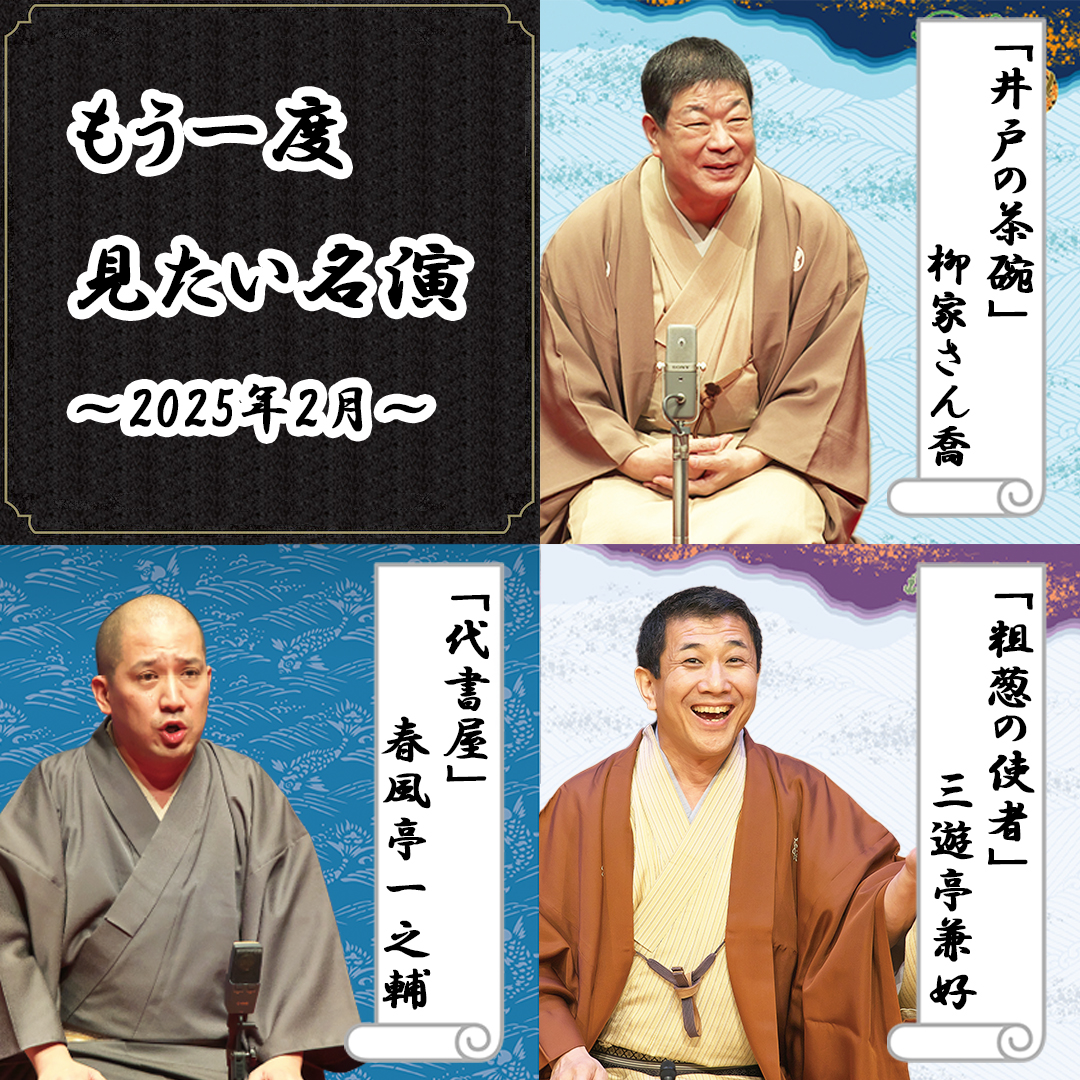この秋は久しぶりに落語の学校公演に行った。某県内トップの進学校。生徒さんは恐らく初めて経験する落語に壁を作らずに前向きで、よく聴き、よく笑い、よく拍手。新鮮かつ間の良い反応で、こちらの気分も上がりまくる。
この学校は3年前にも訪れ、先月急逝された紙切りの林家二楽師匠は当時「この学校は『学校寄席の神様』が俺たちにくれたご褒美だ!」と感激していた。たびたび厳しい状況をくぐり抜けてきた人だから言える魂の叫び。
学校公演によく行く芸人の意見を集約すると、「生徒が笑うか否かはその学校の偏差値と比例する」。勉強のできる学校はよく笑い、そうでない学校は笑わない…もしくは最初から聴かない。
芸人の腕の問題と言いたければ言えばいい。でもこれがほぼ事実なのだ。もちろんどんな学校でも手は抜かない(つもり)。一席終わったあと、生徒の数人でも目を輝かせて拍手してくれれば、やったかいがある。「子供たちが最初に聴く落語が自分の落語」という責任の重さを思えば、偏差値がどうこうと言っていられない。
年1回、50人規模でやっている小さな独演会が今年で19年目を迎えた。初回に親に連れられケラケラ笑っていた6歳の子が、25歳の大学院生になった。いつもおばあちゃんと来ていたが、「祖母は外出が難しくなって…」とのことだった。
「最初来たときのこと覚えてる?」「楽しかったですよ」「大人ばかりの空間によく来てたね」「最初が面白かったからまた行こうと思いました。面白くなかったら来なかったかな」。背筋が伸びた気がした。
面白くないと行かない。至極当然のことだが、案外忘れがちな事実。お客はなんとなく来てくれるものではないのだ。笑わない、とか言ってられない。笑わせる、のだ。笑わせないとその子と落語との縁が切れてしまう。笑わせろ、俺。目が覚めた。収まったこと言ってすいません。よし、今日もがむしゃらに落語のタネをまき続けよう。
【直球&曲球】 春風亭一之輔 子供たちが最初に聴く落語への責任





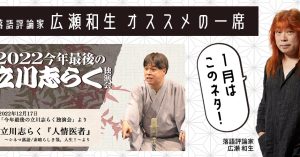
-300x157.jpg)

 X
X
 Facebook
Facebook
 LINE
LINE