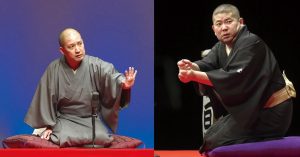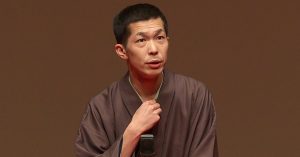2014年の「落語一之輔一夜」から始まった東京・よみうり大手町ホールでの春風亭一之輔ネタおろし独演会シリーズ。2023年11月からは春と秋の「落語一之輔春秋三夜」となっている。2025年4月に開催された「落語一之輔春秋三夜2025春」の演目は以下のとおり。
●4月18日(金)
春風亭貫いち『真田小僧』
春風亭一之輔『ちりとてちん』
春風亭一之輔『ぜんざい公社』
~仲入り~
春風亭一之輔『たちきり』
●4月19日(土)
春風亭㐂いち『湯屋番』
春風亭一之輔『人形買い』
春風亭一之輔『夢の酒』
~仲入り~
春風亭一之輔『佃祭』
●4月20日(日)
春風亭与いち『黄金の大黒』
春風亭一之輔『普段の袴』
春風亭一之輔『岸柳島』
~仲入り~
春風亭一之輔『紺屋高尾』
一之輔が「最近自分に起こった話」を気ままに語るマクラは本当に面白い。この「春秋三夜」では毎晩一席目に「爆笑マクラ+滑稽噺」、二席目に「ネタおろし」、そして三席目に「大ネタ」という構成だった。
<4/18>
「食通気取りの男に腐った豆腐を“珍しい料理”と偽って食べさせる」噺には江戸落語の『酢豆腐』と上方落語の『ちりとてちん』がある。上方落語をルーツとして東京に定着した演目は数多いが、『ちりとてちん』は『酢豆腐』を元ネタにして上方で独自の発展を遂げ、それを東京の演者が逆輸入した珍しいケース。五代目小さんが得意としたことで東京でも数多くの演者が『ちりとてちん』を演じるようになった。一之輔の『ちりとてちん』は、前半の「世辞のいい男が美味しい料理を喜んで食べる」場面に個性的な演出が施されて実に面白く、後半への仕込みに終わっていない。後半の“腐った豆腐と格闘する男”をダイナミックに表現する熱演も爆笑モノだ。
この日のネタおろしは『ぜんざい公社』。上方の『改良ぜんざい』を元ネタに、昭和20年代に桂米朝が「国が設立した“ぜんざい公社”にぜんざいを食べに行った男がお役所仕事の形式的な対応に振り回される噺」として創り上げた新作落語。二代目桂小南が東京へ持ち込み、所属する落語芸術協会に広まった。“ぜんざい公社”という設定と話の展開の“いかにも戦後の新作”感が中途半端に時代錯誤で、すたれていく運命にある噺と思われたが、一之輔は独自の台詞を大量に持ち込み、サゲも変えて、令和の今だからこそ一回りして新鮮に思える“バカバカしい噺”として蘇らせた。噺に入ったとき、ネタおろしの演目としてあまりに意外な選択で驚かされたが、ここまで“自分の噺”に仕上げたのはさすが一之輔だ。
純情な若旦那と一途な芸者の悲恋を描く『たちきり』は、上方落語屈指の大ネタ『たちぎれ線香』を三代目小さんが東京に移植したもの。この日は三席とも「上方落語を東京に移した噺」だったということになる。一之輔は2020年10月の「落語一之輔三昼夜」千秋楽でネタおろししている。滑稽噺でのハジケた一之輔とはまた別の、正攻法で人情噺を演じて観客を引き込むスケールの大きな演者としての魅力を堪能できる一席だ。
<4/19>
一席目の『人形買い』は元々「長屋の神道者が子供の初節句でちまきを長屋に配ったので、お返しに祝いの人形を買いに行く」という噺で、三代目三木助や六代目圓生の演目だが、“神道者”という設定に大した意味はないので、今の演者は「大家がちまきを配った」という設定にしている場合が多い。長屋を代表して人形を買いに行った二人が、候補の人形二体のどちらを買うか迷い、長屋に持って帰って易者や講釈師に相談するという展開だが、後半の“易者”“講釈師”のくだりが面白くないので、大抵は途中の「小僧が二人の供についていく」ところで終える。一之輔もまさにそういう演り方で、ベースは三木助の型だが、「買い物に行く二人のバカバカしいやり取り」や「供に来た小僧のおしゃべり」を大きく膨らませ、サゲも独自に考案している。登場人物それぞれの暴走っぷりは一之輔の真骨頂。この噺をこんなに面白く語れる演者は一之輔しかいない。
ネタおろし『夢の酒』は八代目桂文楽の十八番。明治の初代圓遊が『夢の瀬川』という長い噺の一部に小咄を付け加えて短い一席ものとした。一之輔は若旦那の女房が「亭主の夢に嫉妬する」という状況のバカバカしさを際立たせ、錯乱する嫁に閉口する大旦那をコミカルに描いて笑わせた。若旦那と同じ夢を見て女に説教してくれと無理な要求をする嫁の「お父さんならできます!」に対する大旦那の「その信頼はどこから?」、「私が行くよりお前が行った方が」と言う大旦那への「私がその女を目の前にして言葉だけで済むとは思えません!」といったやり取りの可笑しさは、さすが一之輔だ。
神田お玉が池の小間物屋、次郎兵衛が佃祭から帰ろうと最終の渡し舟に乗ろうとしたところ、かつて命を助けた若い女に引き留められ、舟に乗らなかったことで命拾いをする『佃祭』のテーマは「情けは人のためならず」。一之輔は、次郎兵衛が死んだと思い込んだ人々のドタバタで笑わせながら、「いい噺を聞いた」という心地好い余韻を残してくれる。次郎兵衛を引き留めた女の上品さ、その亭主である船頭の江戸っ子らしい爽やかさが印象的。与太郎の可愛さも群を抜いている。
<4/20>
一席目『普段の袴』は八代目正蔵や五代目小さんの演目で、現代では柳亭市馬が頻繁に寄席の高座に掛けている。一之輔の『普段の袴』も市馬の型を受け継いでいるが、トボケた味わいの“罪のない噺”として演じる市馬とは異なり、一之輔が演じる“真似して失敗する男”の突き抜けたマヌケさは豪快極まりない。大家宅でのやり取りも道具屋での見事な失敗っぷりも、何度聴いても爆笑モノだ。
『岸柳島』は師匠である春風亭一朝が得意とする噺だけに、今回がネタおろしとは意外だったが、なるほどそう言えば一之輔の『岸柳島』は聴いたことがなかったなあ、と合点。煙管というアイテムが重要なモチーフとなる『普段の袴』を一席目に持ってきて、その中で煙管に関していつになく詳しく説明したのは、侍が舟から川に煙管の雁首を落としたことが発端となる『岸柳島』への布石だったのかもしれない。
高嶺の花である最高級の花魁「高尾」に紺屋の職人である久蔵が夫婦になる人情噺『紺屋高尾』の演出には、大きく分けると六代目圓生の系統と立川談志の系統の二種類があり、一之輔が演じているのは圓生系で、久蔵を高尾に会わせる医者の名は「藪井竹庵」ではなく、お玉が池の「武内蘭石」。一之輔は二〇一二年の初演以来まったく演じていなかったこの噺に新たな演出を施して二〇二〇年に再演、独自の『紺屋高尾』を作り上げた。久蔵が「夜桜の晩に花魁道中で目と目が合った高尾が微笑んでくれた」と思い込んで恋に落ち、高尾の錦絵を眺めているうちに「でも、この人とは会えないんだ」と思い悩むうちに病の床に着く、というのが一之輔の演出で、久蔵の一途な思いに応えて年季明けの三月に来てくれた高尾は久蔵を見つめ、「会いたかったわ。綺麗な目……あの夜桜の晩も、なんだか目が合ったような気がしやす」と呟く。さりげない中にも感動を呼び起こす素敵な演出だ。随所に笑いを盛り込んだダイナミックな構成も見事。泣かそうとするのではなく、あくまで爽快な噺として演じた一之輔ならではの名演で「落語一之輔春秋三夜2025春」はお開きとなった。
落語一之輔/春秋三夜 2025春
オンライン配信視聴券、好評発売中!全三公演通し視聴券には千穐楽終了後、一之輔師匠が公演の感想をインタビューした特別特典映像も!
ご購入後、視聴ページに記載のURLからご覧いただけます。
■視聴券
第一夜 5月16日(金)10:00まで販売 18:30まで視聴可
第二夜 5月17日(土)10:00まで販売 17:30まで視聴可
第三夜 5月18日(日)10:00まで販売 17:30まで視聴可
▷視聴券=2,500円
▷視聴券(グッズ付)=5,000円(送料・手数料込)
■全3公演通し券
販売期間:~5月16日(金)10:00
配信期間:各公演の配信期間に準じる
▷全3公演通し視聴券=6,500円
▷全3公演通し視聴券(グッズ付)=9,000円(送料・手数料込)
ご購入はチケットぴあ、e+にて!

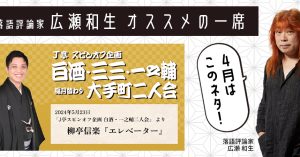
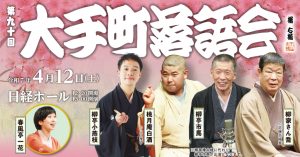
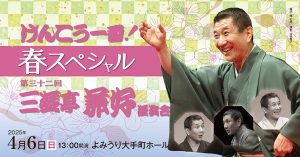
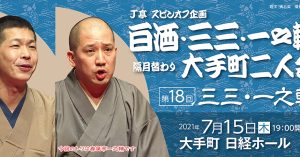



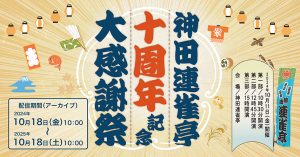

 X
X
 Facebook
Facebook
 LINE
LINE