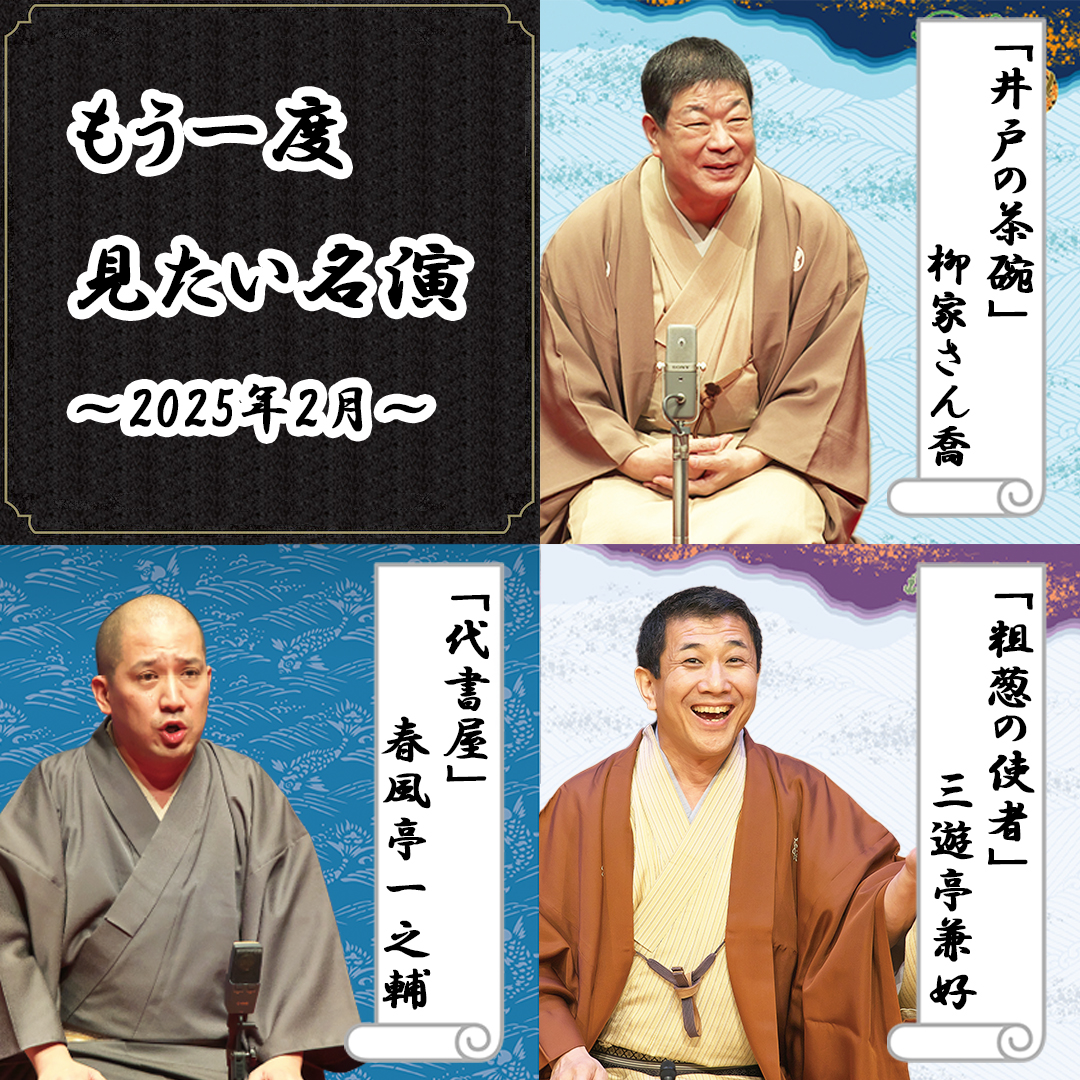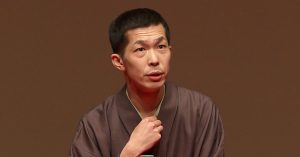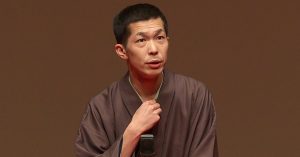2025年7月10日(木)「J亭スピンオフ 桃月庵白酒・春風亭一之輔 大手町二人会」@日経ホール
演目は以下のとおり
柳家小太郎『家見舞』
桃月庵白酒『転失気』
春風亭一之輔『不動坊』
~仲入り~
春風亭一之輔『寄合酒』
桃月庵白酒『鰻の幇間』
開口一番は柳亭左龍の一番弟子、柳家小太郎。演じたのは、以前は『肥がめ』と呼ぶことが多かった演目だが、今は綺麗に『家見舞』とすることが多い。道具屋の外に置いてある瓶に目を付けて店に入る場面から始める単刀直入なやり方で、「それは水瓶にはなりませんよ」と店主が言う理由を二人組がなかなか理解できないのが面白い。兄貴分が「随分オリが出てるな。今度フナを持って来てくれ」と言うと「フナには及ばない、さっきまで鯉(肥)が入ってた」が本来のサゲだが、小太郎はその前の「おい、水を一杯持ってきてやれ」まででサゲるやり方。“肥”を“コイ”と発音する江戸弁がわかりにくい現代ではむしろこの方がいいかもしれない。小太郎は二ツ目に昇進してまだ1年半だが、端正な口調と聞きやすい声、落ち着いた高座態度などが実に好ましく、将来有望だ。
白酒が一席目に演じた『転失気』は寄席で頻繁に演じられる前座噺だが、白酒ほどの技術とセンスがある演者の手に掛かると格段に面白くなる。こういう噺でも新鮮に聞かせてくれるのが白酒の真骨頂だ。この日(7月10日)はリアルタイムで関東一帯をゲリラ豪雨が襲い、特に会場入りする時間帯の会場付近は激しい雷雨に見舞われていて、その話題をマクラに盛り込むのは白酒の通常運転だが、この日の白酒は『転失気』本編の中にもアドリブで“土砂降りの雷雨”設定を盛り込んで爆笑させた。聞きなれた前座噺に予期せぬ一言が入るだけで雰囲気がガラッと変わる“ライヴの妙”が嬉しい。他にも随所に“古典らしからぬ会話”を加えて笑わせたのは、さすが白酒。「やっぱり落語は演者次第だ」と思わせてくれる素敵な一席だった。
一之輔が演じた『不動坊』は上方から三代目柳家小さんが東京に移した噺で、五代目小さんが得意としてポピュラーになった。一之輔は小さん直系の柳家小里んから“柳家の型”を教わっているが、もちろん独自の演出を大幅に加えている。特に一之輔らしさが顕著なのは“お滝さん大好き非モテ三人組”の描き方で、二言目には「せっかくだから」と繰り返すチンドン屋の万さんが愛おしい。マヌケな失敗をした万さんを徳さんが責めまくり、泣き出した万さんが逆ギレする場面の可笑しさは一之輔ならでは。男子校ノリの“部室落語”の典型だ。前半の浮かれた吉兵衛の湯ぶねでの独り芝居も実に楽しい。この日は白酒に続いて一之輔もアドリブで“雨”設定を導入、三人組が土砂降りの雨の夜に屋根の上で繰り広げるドタバタはいつもに増してバカバカしい。この日限りのスペシャルな『不動坊』、これぞライヴの醍醐味だ。
一之輔の二席目は寄席でよく演じる『寄合酒』。元々は上方落語の『ん廻し』の前半を独立させたものだ。一之輔は一門の春風亭正朝に教わっている。コロナ禍の数年前からよく演じるようになった一之輔は、数の子のくだりで乾物屋のオヤジに「キャベツは売ってないのか」と追い詰める演出を加えて可笑しさをブーストさせている。与太郎が拾ってきた味噌のくだりの可笑しさも特筆モノ。鰹節のダシ汁のくだりでサゲるのが普通だが、一之輔はそれを通り越して意外(かつ強力)なサゲに持っていく。
白酒のトリネタ『鰻の幇間』は志ん生をルーツとする古今亭の型がベースだが、汚くて不味い鰻屋の“ダメさ”設定で徹底的に遊んでいるのがミソ。一八が客の前で調子よく振る舞う場面でさえ既にダメな店であるのが垣間見えるのは白酒ならではの工夫。後半で無愛想な女中を相手に次第に怒りが増していく一八の描き方も絶妙だ。(ちなみに白酒の『代書屋』には“小さんの本名”が出てくるが、『鰻の幇間』には“圓生の本名”が出てくる) 女中に文句を言いまくって階段を降りる際にもダメ押しの笑いを白酒のブチ込むサービス精神に脱帽。白酒一流の演出力と演技力を堪能させるこの一席にも“雨”設定がチラリと出てきたのが嬉しい。リアルタイムのゲリラ豪雨がもたらした“スペシャルなライヴ”の一夜だった。



-300x157.jpg)


 X
X
 Facebook
Facebook
 LINE
LINE