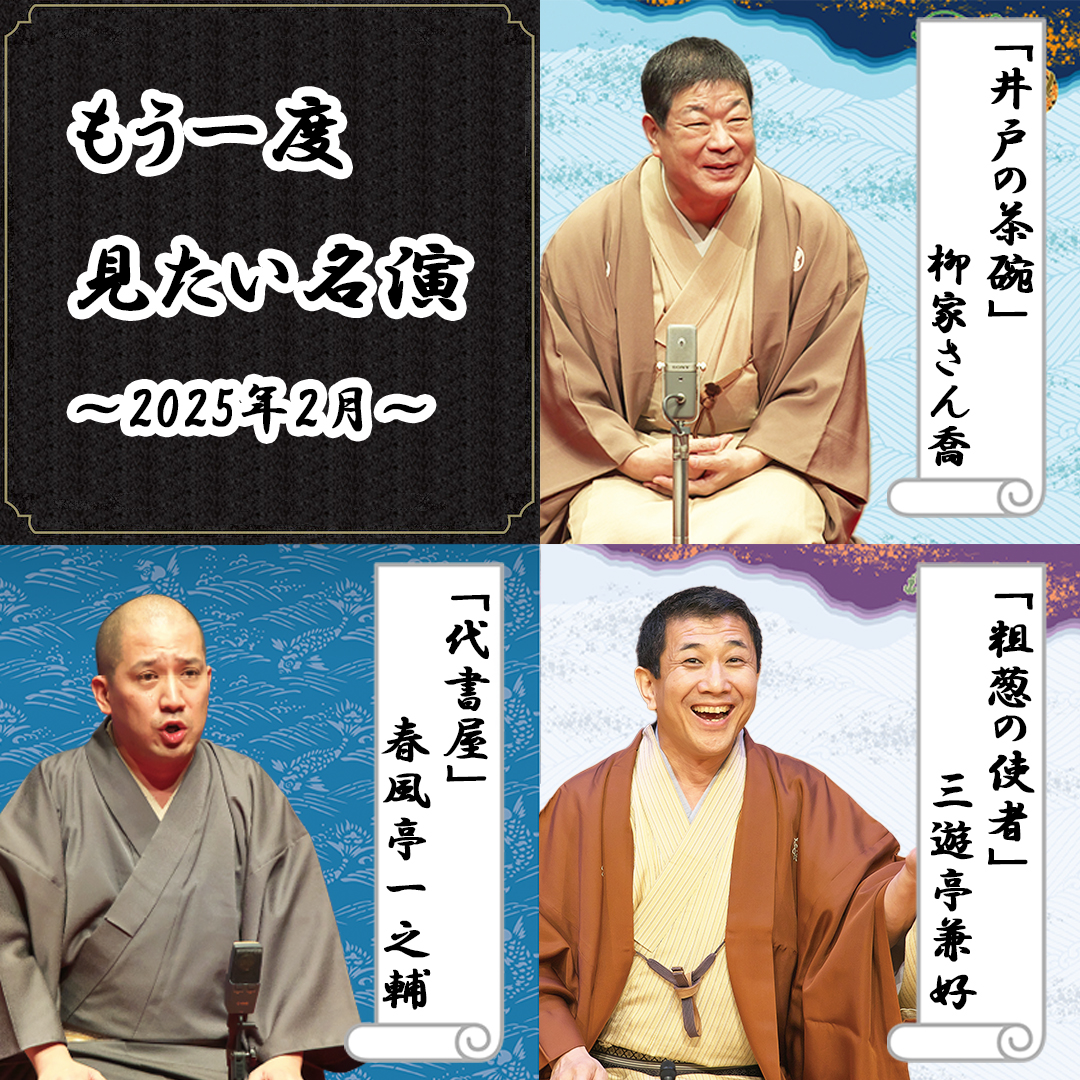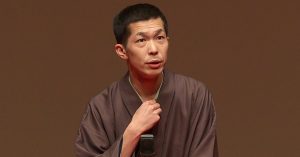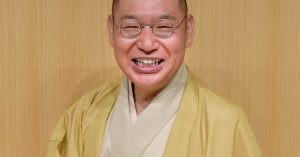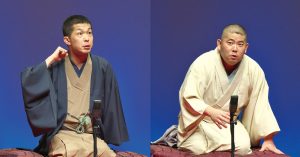2025年3月6日(木)「J亭スピンオフ36 桃月庵白酒・柳家三三 大手町二人会」@日経ホール
演目は以下のとおり
春風亭㐂いち『やかんなめ』
柳家三三『浮世床(将棋)』
桃月庵白酒『抜け雀』
~仲入り~
桃月庵白酒『茗荷宿』
柳家三三『崇徳院』
開口一番を務めた㐂いちは春風亭一之輔の一番弟子。演じたのはやかんを舐めると持病の癪が収まるという婦人を救うため、通りがかりの武家が下女の頼みを聞いて婦人に禿げ頭を舐めさせる『やかんなめ』。埋もれていた演目を柳家小三治が1982年にNHKの企画で発掘して得意ネタにしたもので、弟子の柳家喜多八や柳亭燕路らが受け継いだことで広まった。頭を舐められるという災難に遭う武家を、あくまで“品格と愛嬌を併せ持つ愛すべき人物”として描くことが肝要な噺であり、笑いを求めるあまり下品になってしまってはいけない演目で、㐂いちはそこをきちんと踏まえていたのが嬉しい。
髪結床で順番待ちをしている町内の若い連中の暇潰しのあれこれを描く『浮世床』は、全編通してサゲまで演じるとかなり長くなるため、ロクに字が読めないのに「太閤記」をひもといている男をからかう「本」や、女にモテて寝不足で弱ってるという男の自慢話を聞く「夢」といったパートがピックアップされることが多いが、この日の三三が演じたのはヘボ将棋に興じている二人に悪戯を仕掛ける「将棋」。こういう地味なパートをあえて選ぶのが三三らしいところで、延々と続く他愛のないやり取りで聞き手を引き込む“落語の巧さ”に感心させられる。
宿屋に泊った無一文の絵師が借金のかたとして描き残した雀の絵が奇跡を起こす『抜け雀』は五代目古今亭志ん生の演目で、倅の古今亭志ん朝が十八番とした。白酒の『抜け雀』は古今亭の伝統を踏まえながら独自の台詞廻しを随所に交えて笑いどころが多く、気が弱い宿屋の主人のトボケたキャラが際立っていて実に可笑しい。従来のサゲは「私は親不孝だ、親を籠かきにした」だが、なぜ籠かきにすると親不孝なのかがわかりにくいので、マクラなどで「昔の駕籠かきには悪党が多くて旅人に嫌われた」云々といった仕込みを入れる演者が多い(立川志の輔は登場人物の独白で自然に仕込むという工夫を施している)。だが白酒はサゲそのものを変えることで“仕込み”を不要とした。全編を貫く滑稽味を補強する現代的なギャグが実はサゲに結びつくという意外さは白酒ならではの素敵な発想だ。『抜け雀』に限らず白酒にはこの手の“仕込みを不要とするためのサゲの改変”が少なくない。この意欲は大いに評価されるべきだろう。
「茗荷を食べすぎると物忘れがひどくなる」という俗説がテーマとなる『茗荷宿』には上方も含めて幾つかの異なる演出があるが、白酒は大師匠に当たる十代目金原亭馬生のシンプルな型をベースにしつつ、枝葉を切り捨てて宿屋の夫婦と飛脚とのやり取りに焦点を絞り、徹底的に軽くてバカバカしい噺として再構成した。滑稽噺の申し子たる白酒の真骨頂がここにある。
恋煩いで寝込んだ若旦那の一目惚れの相手を崇徳院の有名な和歌を手掛かりに探す『崇徳院』は、もともと初代桂文治が作ったとされる上方落語で、戦前は“珍品”のような扱いだったというが、三代目桂三木助が東京で演じて広く知られ、さらに古今亭志ん朝も得意としたことでポピュラーになった。志ん朝の演出では茶店で出会ったお嬢さんが短冊を取り出して「瀬をはやみ 岩にせかるる 滝川の」と書いて渡したことになっているが、三木助の演出は「どこかの枝から落ちてきた短冊をお嬢さんがじっと見つめた後に若旦那に渡した」という、偶然性の高い成り行き。三三は三木助系の演出を独自の台詞で膨らませてメリハリを効かせ、生き生きと演じた。“お約束”のやり取りを割愛してテンポ良く演じ、現代的なギャグやこの日限りのアドリブもサラッと紛れ込ませる細やかな工夫には一種のサービス精神も感じる。滑稽噺でありながら、若旦那とお嬢さんの恋の成就に心がホッコリして人情噺のような感動すら覚えるのは、演者である三三の人間的魅力によるものだろう。爽快な後味を残してお開きとなった。





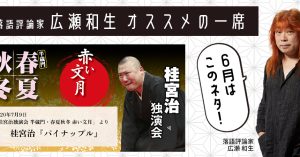
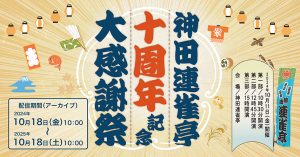

 X
X
 Facebook
Facebook
 LINE
LINE